「U-21 Jリーグ」が2026-2027シーズンに発足する。一見して順風満帆のJリーグだが、その裏では控え選手のリーグが立ち上がっては消滅するという歴史を繰り返してきた。多くの優秀な選手を輩出するようになった今でも依然として「若手育成が機能不全に陥っている」という課題意識がある。その原因と育成を成功に導くために必要なことについて考えてみよう。
敷居が高くなった理由
Jリーグは、ポストユース(19歳~21歳)と周辺年代の選手育成・強化を目的に「U-21 Jリーグ」(仮称)の創設を決定した。11クラブが参加し東西2リーグ制で2026-2027シーズンに開幕することも発表された。
東が、浦和レッズ、FC東京、東京ヴェルディ、川崎フロンターレ、清水エスパルス、ジュビロ磐田。西が、名古屋グランパス、ガンバ大阪、ヴィッセル神戸、ファジアーノ岡山、V・ファーレン長崎となる見込みだ。
名乗りを上げたオリジナル11のクラブの顔ぶれを見ると「大都市周辺のビッグクラブ」「育成が得意なクラブ」「サッカーが盛んで多くの名選手を輩出する地域のクラブ」「成長志向のクラブ」という分類ができるだろう。
Jリーグ理事会において樋口順也フットボール本部長は「参加する11クラブはトップチームの状況に応じて調整をするのではなく、J3リーグに参加するくらいの覚悟を持って試合日程を組んでいく。平均8,000~9,000万円の投資案件」と述べた。
「U-21 Jリーグ」は、育成をしたいからといって気軽に手を挙げられる条件ではない。ハードルが高くなった理由として、過去に失敗を繰り返してきた経緯が挙げられる。(下に記事が続きます)
なぜリザーブリーグは安定開催できないのか?
Jリーグ発足前後に始まったサテライトリーグは、形骸化や財政難などから2009年で終了し2016年〜2017年に復活したが、その後が続かず。Jリーグ育成マッチデーが2018年と2019年に開催され、それを発展させたJエリートリーグが2021〜2022年に開催されたが長続きしなかった。JリーグU-22選抜(2014年〜2015年)やJクラブのU23チーム(2016年〜2020年)がJ3に参戦したが、やはり続かなかった。
続かない根本的な理由として、Jクラブの運営はトップチームが最優先だということが挙げられる。大学や高校は教育機関であり、選手から学費を徴収して教育機会を提供している。一方で、Jクラブはプロの興行団体であり、選手には報酬を支払っており練習生であっても付帯する諸費用は発生する。したがって、財政難になると経費削減の対象になりやすいのだ。いくら育成をしたいと言っても、経済合理性がないと継続できないという懐事情がある。
高校や大学といった伝統的な教育機関は、多くの選手の受け皿になっている。学校でスポーツが行われるのは日本の大きな特徴で活用すべきだが、不十分なところもありJリーグがその隙間を埋める必要がある。(下に記事が続きます)
なぜ若手のリーグが必要なのか
若手選手の育成には、期限付き移籍という方法もある。しかし「直近でトップチームで出場するかもしれないのでクラブに残したい」あるいは「クラブ内の環境やスキームで育てたい」という場合もある。
そして不運にも出場機会に恵まれないと、飼い殺しという憂き目に遭う。本来は伸び盛りであるはずの世代の選手が燻り、腐っていく状況が生まれるのだ。この現状を打破したいというのは、各クラブの共通認識だろう。
なぜ今、U-21リーグが立ち上がることになったのだろうか。
売上高が最も多い浦和は102億円で2年連続で100億円を超えている。J1・J2・J3の内7〜9割のクラブ数、特にJ1の94%のクラブの売上高が増加している状況で、トップチーム人件費も6~7割のクラブが増加傾向にある(Jリーグ公開データ)。伸びた売上をチームの質の向上に再投資できる状況が整ってきているのだ。(下に記事が続きます)
広い視野と戦略の欠落
Jクラブ関係者たちは、あくまでもトップチームの強化の延長として育成を考えてきた。トップチームの収益を育成に投資し続ける余力と覚悟があるクラブは、それでもいいだろう。しかし、離脱するクラブが後を絶たなかったら、結局リーグは立ち行かなくなる。
リーグ全体として、しっかりとした戦略を意識すべきだろう。「観戦いただくのが大事で、お客様を入れる環境を整えること、全試合のインターネット配信を予定しています。放映権のセールスも進めたいと思っています」と樋口順也フットボール本部長は述べる。これは、一歩前進だ。
Jリーグで、リザーブチームの見せ方を工夫しているクラブが一体いくつあるだろうか。「トップチームの下部組織」という自分たちの考えをファンに全面的に押し付けてはいけない。例えば、レアル・マドリードのリザーブチームである「レアル・マドリード・カスティージャ」は、マドリード地域にあったカスティーリャ王国にちなんで命名されている。
控え選手は、モチベーションの維持に苦労する。だから、アイデンティティを与えて、多くのファンの前でプレーしてもらえば、やる気が向上し成長も促されるというものだ。
集客という観点においては、高校野球や高校サッカーはアマチュアの大会なのに、なぜあれだけ人気があるのか考えてみてほしい。アイドル総選挙も参考になる。成り立ちが異なるため高校スポーツや芸能界と同じ路線は、そもそも無理だが、例えば若年層や女性、ライト層などターゲットを意識したマーケティングも行うべきだろう。
ヨーロッパのクラブでも、セカンドチームのマーケティングまで手が回っているクラブはほとんどない。トップチームが稼ぎ頭で育成に投資できるだけの潤沢な予算があり、必要ではないと考えているのだろう。
しかし、Jリーグのリザーブリーグはこれまで紆余曲折を続けており、しっかりとしたブランディングと収益構造について考える必要があるだろう。(下に記事が続きます)
国際見本市という位置づけ
欧州では育てて売り、その利益でクラブを運営するシステムが確立している。中堅どころでは、積極的に若手を獲得するクラブが多い。ビッグクラブは、若手を手広く抱え込んで期限付き移籍で育ててチームを強化している。
日本は急速に選手が育つ国になってきた。国際移籍は、原則として満18歳と定められている。Jクラブで出場機会がない選手たちは、このレーダーから消えることになる。折角、適齢期になったのにデータも映像もなければ、クラブは獲得を検討するのが難しく二の足を踏んでしまう。
まだ成長段階にありJリーグのトップチームで起用されていない選手であっても、欧州クラブが1億円で獲得することは十分に考えられる。選手の展示場という視点も持つべきで、データもしっかりと収集して公開すべきだろう。
「U-21 Jリーグ」はトップチームを強化してクラブが成功するための機構なのだから、選手を引き抜かれては元も子もないと思うかもしれない。しかし、その移籍金でまた選手を育てて好循環をつくればよいのだ。現状として、欧州に選手が移籍する大きな流れを変えることはできない。であれば、最大限にその力を活用すべきだろう。そのような活気のあるクラブには、向上志向のある選手が集まってきて、結果的にチームは強化される。
そして将来的に参加クラブが増えれば、日本の育成は厚みを増していくことになる。(下に記事が続きます)
野々村チェアマン「ポストユースは、キャリア形成の重要な期間」
Jリーグの野々村芳和チェアマンのコメント:2026/27シーズンに「U-21 Jリーグ」をスタートすることを決定いたしました。ポストユース年代は、サッカー選手としてのキャリア基盤を形成するうえで非常に重要な期間です。この時期における継続的なプレー環境の確保は、選手のポテンシャルを最大限に引き出すために不可欠です。
日本においては、大学サッカーが重要な育成のルートとなっており、またJクラブも期限付移籍を活用することで、若手選手に出場機会を提供してきました。これらのパスウェイは今後も重要であり続けますが、一方で、クラブが選手の育成を一貫してマネジメントしながら、定期的な試合出場を確保できる環境の補完も必要であり、「U-21 Jリーグ」は、そこにアプローチする取り組みです。
本リーグが、19歳から21歳の選手にとっては成長のステージとなり、また18歳以下の高校年代等におけるスター候補も躍動する場になることを期待し、今後もJリーグ・日本サッカーのさらなる成長に向けて取り組んでまいります。
Pen&Sports ニュースレター(無料)に登録する
スポーツ特化型メディア“Pen&Sports”[ペンスポ]は毎週、無料ニュースレターを配信しています。原田亜紀夫編集長が勝ち負けを伝えるだけに終わらない、舞台裏のストーリーや本質に焦点を当てたコラムをお届けします。読めばニュースの見方が多面的になり、きっと気づきがあるはずです。登録・解除はいつでも可能です。





![Pen&Sports[ペンスポ]スポーツ特化型メディア](https://sports.pen-and.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/スポーツを深くしる手書き_白字.png)


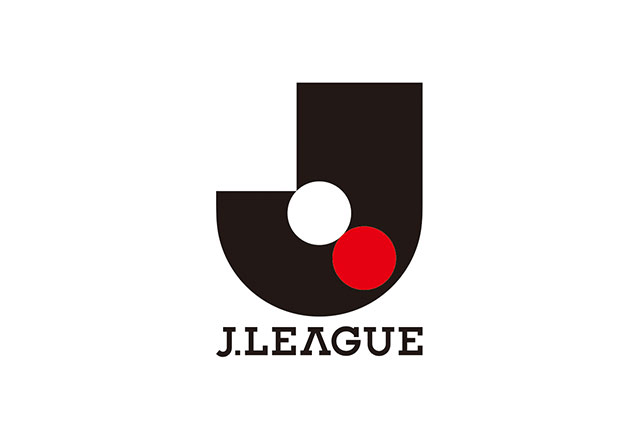





\ 感想をお寄せください /